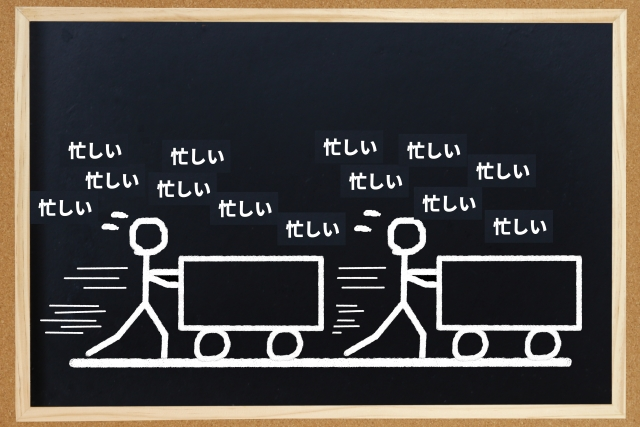
クリスマスや年末年始は忙しい?物流業界の繁忙期・閑散期について解説!
2024.12.23
物流業界で仕事がしたいと考えたとき、繫忙期や閑散期について知っておくことはとても重要です。
いつが忙しくていつが暇なのかが分かっていると休みを取るタイミングが
考えやすくなり、メリハリをつけて働けます。
この記事では、物流業界の繫忙期や閑散期について解説。
一年のうちいつが一番忙しいのか、なぜその時期が忙しくなるのかを詳しくお話します!
物流業界の繫忙期・閑散期とは?
物流業界にとっての繁忙期とは、運ぶ荷物がとても多く忙しい時期のことを
いいます。
人や企業が多く動く時期、年末や特産品の収穫期などが繁忙期にあたります。
逆に閑散期とは、運ぶ荷物が比較的少ない時期のことをいいます。
繁忙期が終わった後、人や企業の動きが鈍くなる時期などが閑散期になる傾向が
あります。
物流業界で働こうと考えている人は世の中の物の流れを把握し、しっかり体調を
整えて忙しい時期に働けるようにしておくことが大切です。
物流業界の繫忙期
物流業界の繫忙期は、毎年ある程度同じです。
世の中の流れに沿って配送数が増えるため、年末年始や家族のイベントなど繁忙期の時期がほとんどが決まっています。
ここからは、物流業界の繫忙期シーズンについてご紹介します。
11月中旬~1月上旬
11月の中頃から1月はじめ頃までは、物流業界で最も忙しい時期のひとつとされています。
物流業界が忙しくなる理由のひとつとして「季節のイベント」があり、この時期であればクリスマス・大みそか・お正月などのイベントが集中しています。
クリスマスプレゼントやおせち、正月の飾りなどを多くの人がインターネットで
買い物をするため、物流業界はとても忙しくなります。
他にもお歳暮を注文する人もいますし、昔と比較すると少なくなったとはいえ
クリスマスカードや年賀状など印刷物の運送も多くなります。
更に年末年始は、バーゲンも行われる時期です。
インターネットで楽しむ人が増えているため、これらの商品の配達も急増します。
この時期は皆が年末に向けて忙しくなるタイミングですが、それは物流業界も同じで普段よりも忙しさが増すため、物流業界で働く人にとっては稼ぎ時といえる
でしょう。
3月・4月中旬
3月や4月など年度末・年度始めは、進学や就職・転勤などで引っ越しをする人が
増えます。
引っ越しをするということはそれだけ物の流れが活発になるため、物流業界も
忙しくなります。
引っ越しの荷物を運ぶことはもちろん、引っ越し先で新しく家具や電化製品を購入する人も増えるため、物流業界は多忙となる時期です。
5月・6月
5月と6月はそれぞれ「母の日」と「父の日」があります。
母親や父親に感謝の気持ちを伝えるため、花やネクタイなどを贈ったりする人が
増えるため、この時期の物流業界が忙しくなるのです。
6月下旬~8月
6月下旬から7月にかけては、お中元を贈る人が増えるため、荷物が増加します。
7月下旬からは夏場は学生が夏休みに入るため、消費が増えます。
お盆休みを使って帰省する人が荷物やお土産の配送を希望することもあります。
夏場は年末年始に比べるとそこまで大きなイベントがないため「繫忙期なの?」と疑問に思いがちですが、物流業界は意外と夏場も忙しいのです。
地域によって繫忙期になることも
物流業界の繫忙期は、地域によって発生することもあります。
発生する時期は「特産品が収穫される時期」です。
お米やカニ、野菜などその時期によって収穫される特産品を運ぶために、
物流がその時期だけ忙しくなります。
他にもスキー場や避暑地など、リゾート地の繁忙期が物流業界の忙しさに繋がる
こともあります。
リゾート地に観光客が集まると旅行用の荷物や購入したお土産を送りたい人が
増えるため、物流業界の需要が高まるのです。
一時的なイベントでも忙しくなる
オリンピックや万博など世界規模の大きなイベントが開催される場合も、一時的ではありますが繁忙期を迎えます。
イベントの開催に伴い道路が規制され、いつもと違うルートで配送しなくてはいけないということも起こりえます。
世の中の動きやニュースを常にチェックしておくと、いざという時冷静に行動できるでしょう。
まとめ
物流業界の繁忙期や閑散期についてご紹介しました。
一般的に忙しいシーズンは、まとめると以下の通りです。
・11月中旬~1月上旬(年末年始)
・3月・4月中旬(引っ越しシーズン)
・5月・6月(母の日・父の日)
・6月下旬~8月(夏休み・お盆)
こうやって見てみると、物流業界は一年のほとんどを目まぐるしく動いていますね。
物流はどんなに不景気になってもなくなるものではないですし、いつも活気がある業界といえるでしょう。
忙しく大変ではありますが、やりがいのある仕事ともいえます。
繫忙期や閑散期を把握して休みを調整し、いつでも体調を万全に整えて、日本の
経済を支える仕事に取り組みましょう。
